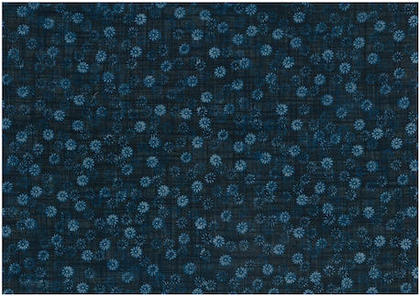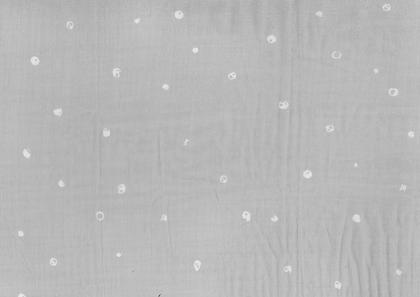2017年 6月
ブランド「登美」の夏の定番のひとつ、「綿スラブローン」。20数年前に松場大吉・登美夫妻が出会い、生地に惚れ込み、以来毎年作り続けているシリーズです。
ありがたいことにファンも多く、毎年この時期になると綿スラブローンの服はできたかな?と名指しで店舗に遊びにいらしてくださる方がいらっしゃるほど。
綿スラブローンを作っているのは、静岡県浜松市に工場を置く創業89年の「古橋織布」。
2017年夏・私たちは、復古創新をテーマに、歴代の柄の中から3柄を復刻する「綿ローン祭」をはじめています。
それに連動して、群言堂公式サイトでは全3回で古橋織布や産地について、また生地を使い続ける登美の想いに焦点を当てたコンテンツを公開します。
まずは、古橋織布が工場を置く産地についてお話させてください。 静岡県浜松市は、江戸時代から綿花の栽培地、明治時代には遠州織物の産地として栄えた土地です。
とはいえ、かつて1,600軒以上あった「織屋」は、時代の流れや担い手の減少につれて今や70軒程度まで減ってしまいました。
古橋織布は、そんな中で伝統と技術を後世に伝えようと不断の努力を続け、今日まで生き残ってきた織屋です。
松場大吉・登美と古橋織布の現在の当主・古橋敏明さんとの出会いは、今から20数年前にさかのぼります。
伝統と実績ある繊維産地として栄えた時代が過ぎ、海外製品が安く輸入されたり、時代の進歩で昔からの織機が淘汰され始めた頃、古橋織布を含めた何名かの当主たちは自分たちで販路を開拓しようと、とある展示会に出展します。
そこに居合わせたのが大吉。「すごい生地と作り手に出会った」と、帰宅するなり興奮しながら話す大吉の姿を登美は今でも鮮明に思い出せるといいます。
大吉と登美が惚れ込んだのは、作り手の姿勢と出来上がる生地の品質の高さ。触れるなりひんやりとして手に吸い付くようで、風合いがほかの生地と段違いに異なる古橋織布の織物に、ふたりとも感動を隠し得なかったのだそう。
古橋織布のモノ作りの現場は、太陽光が最大限に差し込むように作られた北向きの窓がずらりと並ぶ、昔ながらののこぎり屋根を持つ工場です。
その工場の中で、ガチャンガチャンと朝早くから音を立てるのが、古橋織布が愛用するシャトル織機。 シャトル織機とは、高度経済成長期に日本の大多数の織屋が手放した旧式の織機のこと。
最新式の織機であれば、1日あたり400メートル以上の生地を織れますが、シャトル織機はなんとその10分の1以下の速度。 毎日油を指したり、温度や湿度にあわせて機械の調整をしたりと、使用には手間がかかります。
それだけでなく、天然素材の細い糸を使用し織り上げるため頻繁に切れて織機が止まりやすいなど困ることも多いけれど、機械や技術、受け継いできた伝統を継ぎたいと、古橋織布はシャトル織機を使い続けています。
ただ、それだけでは古橋織布独自の風合いの生地は作れません。秘密は、古橋さん自身がお客さまが求める品質に対応できるようにと、試行錯誤を重ね独自にシャトル織機を改良し続けてきたことにあります。
通常よりも5〜10%ほど糸密度を高くし、開口部を15〜20%ほど開いて、ゆっくりと低速で織っていく古橋織布の綿スラブローン。通常よりも手間をかけて織り上げるからこそ、空気を織り込んだようなふんわりとした風合いの生地に仕上がるのだとか。
日本全国に織屋は多数あるといえども、群言堂が古橋織布に特に惚れ込んでしまう理由は、作り手のモノ作りへの想いやこだわりにあったのです。
さて、産地や古橋さんについてのお話は一旦ここまでにして、次回は登美へのインタビュー。古橋織布の生地に惚れ込む理由や本音を、じっくりとお聞きしました。